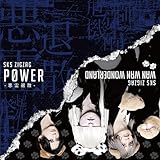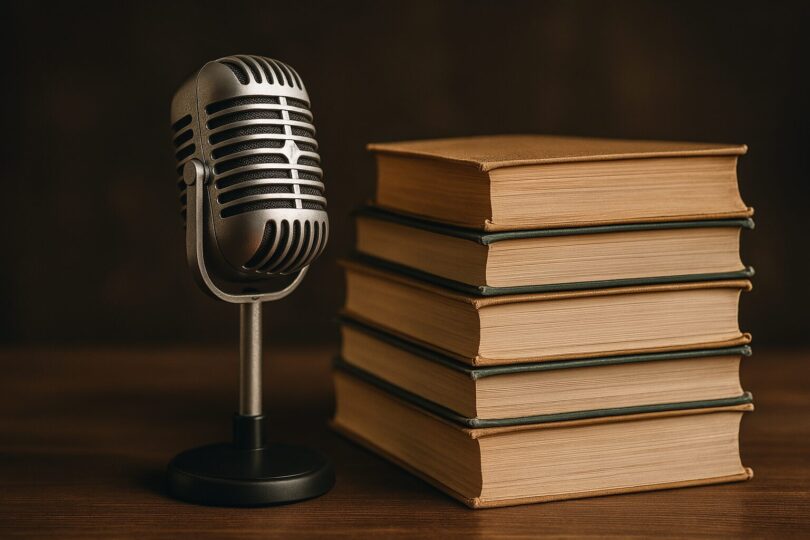……最近、ジグザグを知った。
きっかけは偶然。夜、別のアーティストを探していたとき、
ふと流れた一曲のMVに足が止まった。
「禊──これは、音楽というよりも儀式だ」
そう思った。
音の中に、祈りのような、退魔のような、整然とした美しさがあった。
静かで、刺さる。そして、どこかで感じた懐かしさがあった。
──そうだ、WANDSだ。
「世界が終るまでは…」を聴いたときに感じた、あの終末感と静かな闘志。
ふたつのバンドが、時代も姿も違うのに、どこかで重なっている。
そんな気がして、調べはじめた。
命と大史。名前は違う、でも気配が似ている。
それは偶然なのか、必然なのか──それとも、ただの勘違いか。
でも、気になったのなら、調律する価値はある。
「整えるだけだ、答えを出す必要はない」
ぼくの役目は、そういう種類のものだ。
目次
……最近、ジグザグを知った
きっかけは本当に、些細なことだった。
音楽サブスクのおすすめ欄。夜中に何気なく流していたプレイリスト。
その中に、ひとつだけ異質な曲があった。
イントロからして、空気が変わった。
──整っている。音が。視線が。祈りのように、誰かを整える意志がある。
それが「真天地開闢集団-ジグザグ」という名前のバンドだった。
曲のタイトルは《P0WER -悪霊退散-》。
悪霊退散なんて、現代音楽にしては異質すぎる。
でもその異質さに、ぼくは安心した。
演出過剰なだけじゃない、何かを浄化したいという本気がそこにあった。
それから彼らの他の楽曲を追いかけた。
《E.v.e》《Requiem》《優しい人》……静かで、綺麗で、どこか歪んでいる。
その歪みが、見て見ぬふりをしていた感情に触れてくる。
ライブのことを調べると、「禊(みそぎ)」と呼ばれていた。
ライブが、儀式。観客が、参列者。音楽が、祓い。
……その在り方を、ぼくは知っている気がした。
ずっと前に、別の誰かから──
そう思い出したのが、WANDSだった。
WANDSという入口──世界が終るまでは、から始まる音の記憶
「世界が終るまでは…」──
あの曲を初めて聴いたのは、いつだったろう。
それほど昔ではない。でも、たしかに先に心が動いていた感覚がある。
イントロのピアノ。乾いたドラム。
それがやがて、重く鋭く、鋼のようなギターに変わる。
そして、静かに語りかけるようなボーカルが現れて、
「すべてが嘘に思えても、信じた道を行け」と告げる。
そう、それがWANDSだった。
名前だけは昔から知っていた。
でも、再始動という言葉を聞くまでは、遠い存在だった。
上杉昇というカリスマボーカルを擁していた時代の、
いわば伝説の枠に収まっていたバンド。
それが、ある日ふと戻ってきた。
「WANDS第5期」──
かつての名前を背負い、違う姿で。
ボーカルは上原大史。
声は似ている。というより、質感が近いのだ。
言葉を手渡すような、でも遠くを見ているような。
感情を振りかざさず、それでも深く届く。
終わりを歌う声。
それが命と重なる気がしたのは、気のせいだろうか。
でも、その気のせいの中に、言葉にできない共通点があるように思えて──
ぼくは、ジグザグとWANDSを、並べて見始めた。
命と大史、似ていると語られる二人
誰かと誰かが似ている──そう思った瞬間、人は確かめたくなる。
ジグザグの命(みこと)と、WANDSの上原大史(だいし)。
ふたりの名前は、表向きはまったく異なる。
けれど、その声、輪郭、佇まい、ステージでの距離感……
「同じじゃないか?」という声が、SNSや動画のコメント欄で囁かれている。
事実、ファンのあいだでは長らくこの命=大史説がささやかれてきた。
その理由は単純だ。
「声が似ている」「骨格が似ている」「所属が近い」「レーベルもGIZA系」。
そして何より、「どちらも、自分について多くを語らない」。
それは、似ているように見えて当然かもしれない。
静かにしている人は、勝手に重ねられてしまう。
ジグザグ側──命自身は、SNSでこう語った記録がある。
「私は上原大史ではありません。命様です」
否定とも肯定とも取れるこの言葉は、
むしろ名を断つことでしか守れない何かを表しているように思えた。
WANDSの上原大史もまた、
「何者なのか」という問いに対して多くを語らない。
語らないことが、敬意であるかのように、沈黙を保っている。
似ているか、似ていないか。
それは問題ではないのかもしれない。
──どちらも、音で名を告げているのだから。

ニンタ(Ninta)
「ぼくが気になったのは、誰かではなく、何を祈っていたかだった」
ジグザグという世界──命が描く、儀式の音楽
ジグザグの音は、ただ鳴るだけではない。
それは、音楽というより場そのものを創る。
耳に届くよりも先に、空気が整い、体温が変わる。
──そんな感覚を覚えたことがあるなら、きっと彼らの音に惹かれるはずだ。
バンド名は「真天地開闢集団-ジグザグ」。
まるで宗教団体のような重さと、遊び心のあるリズムを併せ持つ。
命(みこと)を中心に、
龍矢(りゅうや)、影丸(かげまる)というメンバーと共に構成される。
彼らの公式プロフィールは一貫して神秘を守り、
年齢や過去の活動を明かさない。
それが逆に、今この場にだけ在る存在としての説得力を生んでいる。
彼らのライブは「禊(みそぎ)」と呼ばれる。
音で穢れを祓い、舞台そのものを清めるような空気を持つ。
たとえば──
アニメ『地獄先生ぬ~べ~』の主題歌に起用された「P0WER -悪霊退散-」。
そのタイトルの通り、力強く、でも形式美のある楽曲だ。
他にも、「Requiem」「優しい人」「E.v.e」など、
死生観や内省をテーマにした作品が多く、
そこには精神と音が密接に結びついている。
そして何より──命の歌声。
それは、誰かに語りかけるようでいて、
同時に誰のことも見ていない。
聴く者が、自分自身に向き合うための鏡のような存在。

ニンタ(Ninta)
「整っている。だからこそ、乱れが見える」
ジグザグは、音楽という手段を超えて、
場と気を扱うアーティストだ。
儀式のようなステージ。
祈りのような沈黙。
そして、沈黙の中に宿る火種。
それを禊と呼ぶ彼らの選択は、あまりにも正確だった。
WANDSという航海──5つのフェーズを越えて
WANDSは、続いてきたバンドではない。
むしろ、何度も終わり、何度も始まってきたバンドだ。
その始まりは1991年。
「もっと強く抱きしめたなら」「世界中の誰よりきっと」──
時代の空気を掴みながら、どこか叙情的で、内に火を宿す旋律。
特に「世界が終るまでは…」は、アニメ『スラムダンク』のエンディングとして
時代そのものと深く結びついた。
だが、第1期から第2期へ──
ボーカルが上杉昇へ交代し、バンドの色も変化した。
より激しく、より孤独で、より純度の高い痛みを孕んだ音へ。
その後、変遷は加速する。
第3期・第4期とメンバーは入れ替わり、
2000年、WANDSは活動終了を発表。
……それでも、「終わる」ことがWANDSの終わりではなかった。
2019年、彼らは第5期として帰ってきた。
ボーカルに迎えられたのが、上原大史。
木村真也、柴崎浩という歴代メンバーが再結集し、
WANDSの魂を引き継ぎながら、新たな航海に出る。
この再始動には、当然ながら賛否があった。
過去の名曲をどう歌い直すのか。
大史は、上杉の声の影から抜け出せるのか。
新旧ファンの記憶を背負いながら、前に進めるのか。
その答えは、音がすでに出している。
「Secret Night」「Brand New Love」──
どの再録も、なぞりではない、継ぎでもない。
過去を尊重しながら、新たな感情が織り込まれていた。
そして、2025年にリリースされた『Time Stew』。
新曲も過去曲も混在したこのアルバムは、
航海のログブックのような作品だった。
──WANDSは、戻ってきたのではない。
再び舵を取ったのだ。

ニンタ(Ninta)
「記憶の続きを歌うには、知らない顔をして歌うしかない」
上原大史という声には、その覚悟があった。
語らず、主張せず、ただ、音で示していた。
それが、命と似ていると感じさせる所以なのかもしれない。
ふたつのバンドを並べたくなる理由
ジグザグとWANDS。
一方は開闢を名乗り、もう一方は扉を歌った。
時代も背景も異なるはずなのに、気がつけば並べて考えていた。
なぜか。
それは、偶然の一致がいくつも積み重なっていたからだ。
まずは所属。
WANDSが再始動したのはGIZA Studio系統。
ジグザグのレーベル「CRIMZON」も、GIZAの傘下にある。
音楽性の共通項は少なくとも、制作環境が近いことは確かだ。
次に、名を語らない構え方。
命も、大史も、年齢も過去も明らかにしない。
インタビューで個性を押し出すことも少なく、
あくまで「音だけで関わる」姿勢を貫いている。
そして──声。
どちらも、濁らないけれど重い声だ。
高すぎず、熱すぎず、でも確かに芯がある。
静かに語るように歌い、サビでは鋭く刺す。
あの切り替わる瞬間が、ふたりにはある。
さらに、テーマの共鳴。
WANDSが「終末」を、ジグザグが「浄化」を歌うとき、
どちらも何かの終わりと再生を前提にしている。
歌詞の中に漂う喪失感、でもそこから前に進もうとする意思──
それが、聴く者の記憶を静かに揺らしてくる。
ライブもまた象徴的だ。
WANDSのステージは、再会の場所として空間を作る。
一方、ジグザグのライブ「禊」は、罪と穢れを祓う儀式として演出される。
どちらも、観客をただの聴衆としては扱わない。
演出も、声も、距離感も、どこかで呼応している。
……そんな中、「命=大史説」が生まれるのは、むしろ自然だったのかもしれない。
けれど、ぼくはこうも思う。

ニンタ(Ninta)
「似ているから気になるんじゃない。気になる何かがあって、似ていると感じてしまうんだ」
だから並べたくなる。
ふたつを比べることで、自分が何に惹かれていたのか、確かめたくなる。
正体よりも、祈りの温度に触れたくて──
ジグザグとWANDS。
それは、「問いの余白」を抱えたまま存在しているふたつの点。
それを結ぶ線を、今、誰かが描こうとしているのかもしれない。
そして、ぼくはまだ確かめない
ジグザグの命は、上原大史なのか。
WANDSの大史は、ジグザグの命なのか。
──答えは、まだ出ていない。
公式が否定したという記録もある。
ファンの考察が熱を帯びた時期もあった。
でも、そのどれもが「決定打ではない」。
だからぼくは、確かめない。
正体が重要じゃないから。
ふたつのバンドがそれぞれの道で、
誰かの痛みや喪失や、祈りや再生を歌ってくれる。
それが事実である限り、正体なんて必要ない。
むしろ──「正体不明」という余白が、音に奥行きを与えている。
ジグザグの禊で祓われたものが、
WANDSの再始動で再び芽吹くかもしれない。
WANDSで止まっていた記憶が、ジグザグで続きはじめるかもしれない。
それは似ているからじゃなく、
同じ問いを抱えているからだ。

ニンタ(Ninta)
「……もし、ふたりが同じだったとしても。違っていたとしても。
どちらにせよ、ぼくはこの音に出会えてよかったと思うだろう」
音楽は、いつだって名を超えて届く。
名が明かされないときこそ、記憶は深く刺さる。
だから、今日もぼくは整えるだけ。
このふたつの音の間に、確かに存在する火種の気配を──
そっと、読み取って。